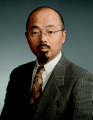┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
┤
| |||
|
(前頁より) 構成物質的な定義から脱却した時、生命の定義は何でしょうか? 多くの科学者の議論の結果、現在では次の条件を満たすものを生命と考え、生命の合成の研究を行っています。 <生命の定義> 1)自己複製できる 2)自己組織化できる 3)自己維持できる 4)自己進化できる このように生命を定義しますと、コンピュータ上で生命を再現することは可能になります。実際、クリス・ラングストンという科学者がこの条件を満たす生命を誕生させました。もっとも、彼は謙虚にこの研究アプローチは従来の生命の研究の補助的な役割を担う方法であると言っています。 こうしたコンピュータ上で生命を創る研究や人工的に創られた生命に対して次のような疑問を持つ人々がいます。 1)このように創られて生命はコンピュータの電源を入れることを前提としており、電源を入れなければ生命の定義は満足されない。 2)生命系であるコンピュータは人間によって先ず最初に創られる。 確かにこの指摘は鋭いのですが、我々を含む地球上の生命は太陽エネルギーを前提としています。太陽エネルギーという電源が切られますと自己維持が不可能となり、複製も進化もがありません。その意味で私たちもコンピュータ上に生きていることと変わりありません。 生命系である宇宙に私たちは生きていますが、その宇宙は人間が創ったものではありません。 このように考えますと生命の概念はコンピュータ上で創られたプログラムにまで拡張して考えても不思議ではないことになります。 なにしろ生命が地球上に誕生するのに6億から10億年の時間を費やしていることと比べると、コンピュータ上での生物の誕生は1987年にスタートして10年も経っていないのです。 |
生命の研究の観点からマルチメディアを考えいますと、マルチメディアのもつ情報統合化の技術は受動的な機能でしかありません。 インタラクティブといっても予め作成されたプログラムに基づいて人間とコンピュータが対話しているのです。本当の対話ではありません。 この受動的な機能を能動的な機能に転換するには生命型のコンピュータの創造が必要になります。 能動的になるとコンピュータは次のようなことのできるようになります。 1)コンピュータから人間に働きかけをすることができる。 2)最初に創ったプログラムが自己進化して新たな動作をする。 3)自己修復、複製、組織化可能なために自然に治癒する事ができる。 生命型コンピュータのイメージが出てきましたか? 更にインターネットの分野で考えますと、インターネット自体を1つの生命体として考えることができます。インターネットを利用するユーザは個体であり、 Webサーバーはそれ自身で自律する細胞と考えることができます。 各細胞は互いにインターネット上でコミュニケーションを計りながら、生命体を構成する役割を担っています。 このようにインターネットを考えると、人間の倫理観、成長度、衰退、、免疫などと比較しながらインターネットの今後のあり方を研究していくことができ、新しい発見が生まれてきます。 マルチメディアの向こうに生命型がある・・・・これが将来の方向です。 会津大学マルチメディア情報センターを見ますと”人工世界”という言葉が使われています。マルチメディアが発展して行き、生命型コンピュータが完成して、この生命型コンピュータが人間に取って代わって色々な仕事を能動的に行うようになります。その結果、創られるであろう社会を”人工世界”と位置づけているところから、この言葉を使った研究室やゾーンがあるのです。 センターを見学されて皆さんが不思議に思ったこの言葉は我々が長期的な視野に立ち、マルチメディアの行き先を予測して名付けた言葉なのです。(以上) | ||

 - 7 -
- 7 -