|
マルチメディアから人工生命へ |
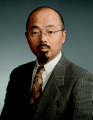
|
会津大学 コンピュータ理工学部 ハードウェア学科 コンピュータ産業学 教授 池田 誠 |
| AIZU-Univ.-MULTI-MEDIA-ESSAY | ||
|
マルチメディアが騒がれてからもう2年の歳月がすぎた。マルチメディアが騒がれた理由はコンピュータがコンテンツ、ネットワーク、ハードウエアに関して”シームレス”な機能を提供できる段階になったことにある。 ”シームレス”とはどういう事なのだろうか? 従来テキスト、画像、CG、音声等は異なるメディアでしたが、デジタル化されることで同一に扱えることになりました。簡単に「デジタルとして扱う」といってもここまで来るには随分技術的な障害がありました。 これらのメディアをデジタル化した結果メディアをインタラクティブに扱うことができ、メディアは容易にその中身を変身できるようになりました。こうしたことからメディアという言葉に代わってコンテンツという概念が出てきました。 従って、コンテンツは多種多様なメディアのカテゴリを捨てて、全てを差別はなくシームレスに処理できる意味を持つことになります。 ネットワークも同じ経緯があります。デジタル化によって、高速で大容量の機能を持ち、しかも双方向性で使えることになりました。特に、インターネットなどが日常レベルで大衆的に使われ始めており、情報を受信する人と発信する人の関係は対等の関係になりつつあります。情報生産の権利をもつ人々が増え、従来の情報権力の社会的な構図には逆転現象が起きつつあります。 ここでも受発信に境界がなくなりシームレスな関係に生じているといえます。 ハードウエアは高速なCPU、様々なメディアのデジタル処理を行うチップが開発され、従来のコンピュータの概念から拡張されました。コンピュータはテレビ、FAX、電話など従来のメディア媒体と区別はなくなり、全てを包含するメディアツールとして進化を遂げています。 シームレスとは今までの概念、カテゴリで考えられてきたものが、新しい概念に統合されていくことを意味しているような気がします。 このようにコンピュータの技術革新は一般の人々が日常的に利用するに余りある機能を搭載している段階にも関わらず、いまだにその進歩に勢いは止まることはない。 人類はこのマルチメディアという言葉に満足していない。 米国で良く言われている言葉があります。「3ヶ月が一年」である。 一般の人が生きている1年の感覚はコンピュータの技術開発では3ヶ月に相当するという意味の言葉です。 息の抜けない駆け足状態の技術革新競争を表している言葉です。 コンピュータの研究開発競争のど真ん中にいると、人類は何故こんなに急いでコンピュータのあらゆる機能を向上させようとしているのか、ふと疑問に思うことがあります。 |
私の感覚では3か月どころではない。1ヶ月単位で新しいものが出現している時代であります。 この勢いでは”マルチメディア”は死語になってしまって当然である。 ふと立ち止まって考えたとき、ある本で読んで文章が思い出された。 カーネギーメロン大学のハンスモラヴィックによると手計算で始まったコンピュータの進化の過程から計算して、2030年頃にはパソコンの能力は人間と同等になるであろうと断言しているという文章である。 2030年と言えば私が80歳位の頃であり、健康に気を付けてしぶどく生きていれば、私も人間の能力になったコンピュータとお目にかかることになります。 人間の能力レベルのコンピュータと比較しますと、マルチメディアなんて騒いでいる現在のコンピュータはまだ実験レベルの代物です。 生物の進化の過程で遺伝子が担っている情報の処理能力は単細胞から、原生動物、は虫類になるにつれて増加して、最大の遺伝子情報をもっているのは人類といえます。人類の情報処理能力もこの数万年の間で飽和状態にきていますが、その人類の脳に匹敵する情報処理を後30年程で完成させようとしているわけですから、多くの技術者がコンピュータの開発に急いでいるのはわかる気がします。 人間をターゲットにすると”シームレス”というレベルではまだまだものたりず、やはり5感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)を扱える生命体レベルをめざしているのです。 会津大学の池戸教授がグラフィックチップの能力の向上をめざし、懸命に研究開発されているのも、コンピュータの能力を人間の視覚認識処理と同レベルにしたいという願望からでしょう。 さて、ハードウエア的には人間と同じレベルになっていくコンピュータを支えるソフトウエアに関する進歩はどうなるのでしょうか? これに関しては、人工生命の研究が鍵を握ることになります。現在、”コンピュータに生命を組み込む”研究が急速に広がっています。 どのようにしたらコンピュータに生命を組く込むことはできるのかという議論の前に、生命とは何かを考えなければなりません。 現在、地球上存在する生命しか生命の対象ではないという議論があります。 こうした議論の根拠は地球の生命系の生命の定義は”蛋白質に依存する構成物質”を基本にした定義から始まっています。しかし、今後蛋白質で構成されていない生命が他の惑星系で発見された場合は生命をどのように定義するのでしょうか?この可能性はないともいえません。 (次頁へつづく) |

 - 6 -
- 6 -
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├
├